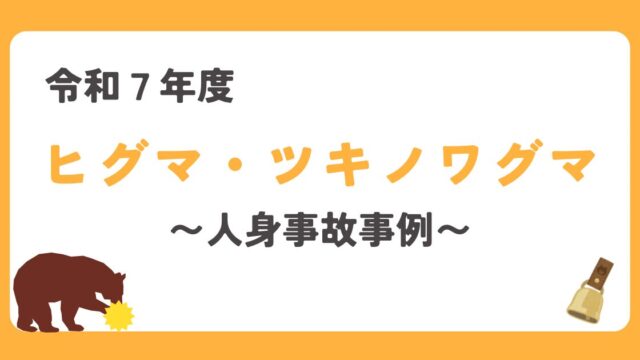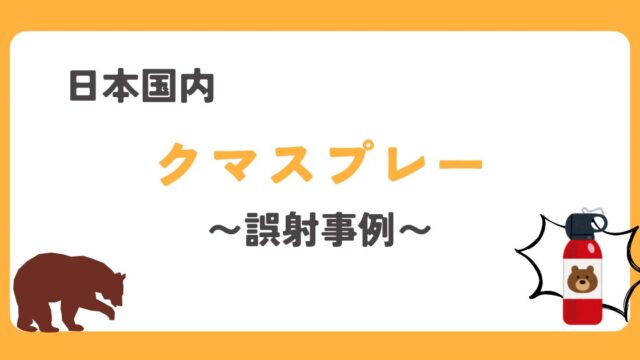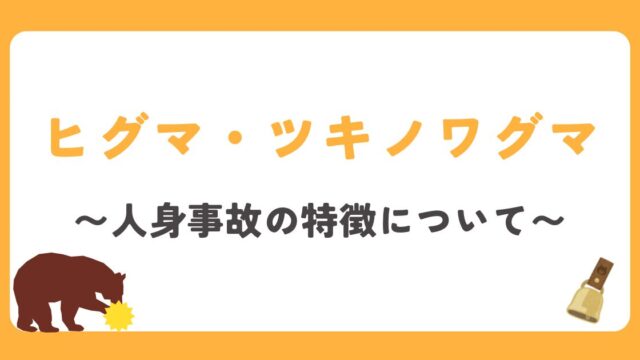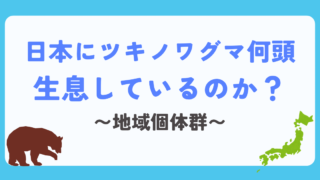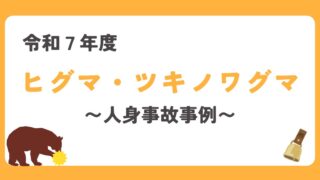クマ類の農林水産被害の特徴と被害対策方法
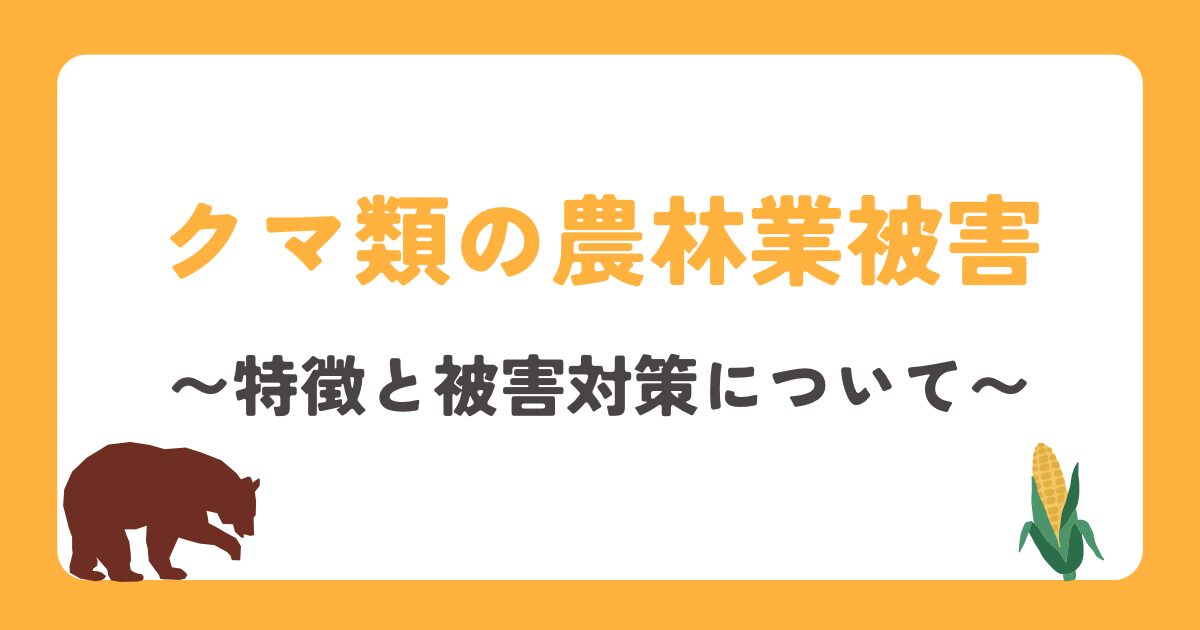
記事の内容
・クマ類(ヒグマ、ツキノワグマ)による農作物被害の特徴
・被害対策方法
クマ類の農林業水産被害の特徴
ヒグマ

ヒグマによる農業被害は平成25年度から増加傾向であり、デントコーン、ビート、牧草、スイートコーン、小麦などに被害が発生しています。令和5年度の農業被害額は3億3千2百万円と、前年度に比べ8千3百万円増加しています(北海道環境生活部自然環境局野生動物対策課)。
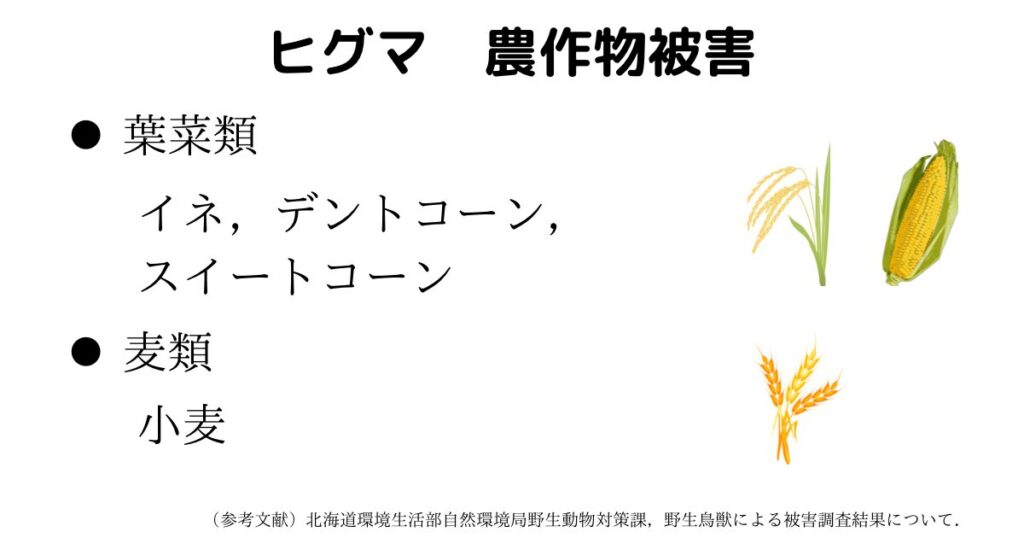
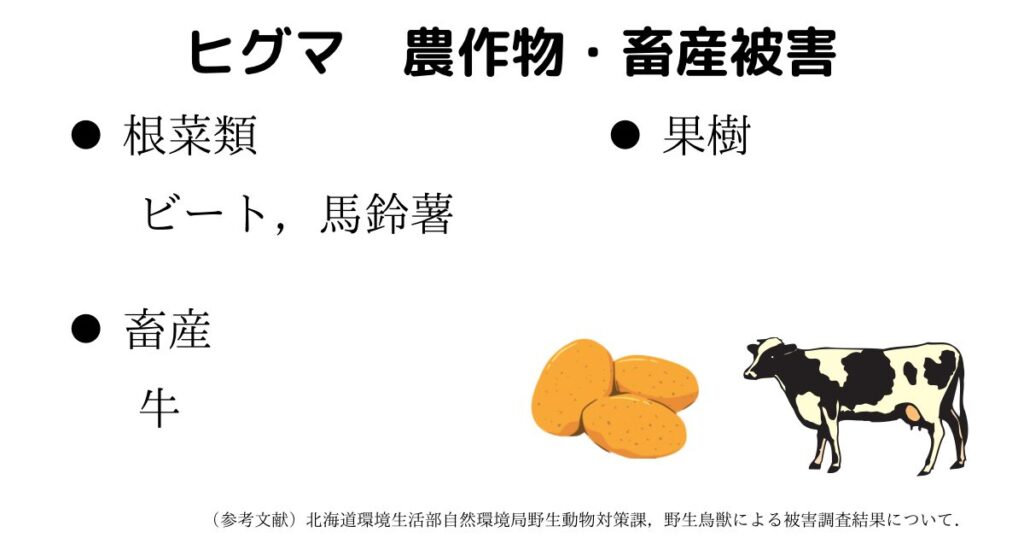
ツキノワグマ
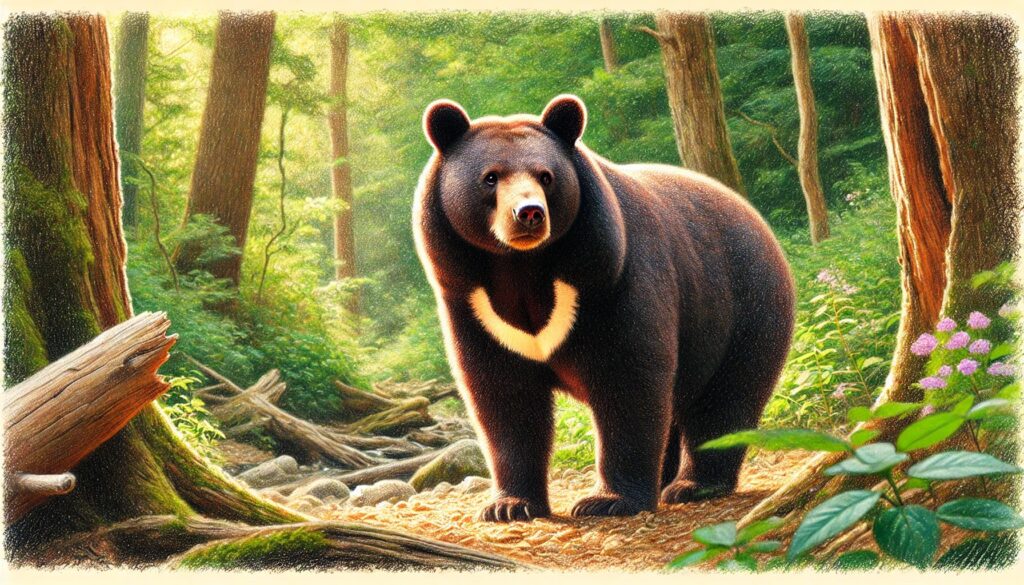
ツキノワグマは人里や集落付近へ出没し、農林作物や家畜等への被害を発生させることもあります。主な農作物被害ではイネ・トウモロコシ・果樹類(カキ・クリ・リンゴ等)に多くの被害が発生します。また、針葉樹の皮を剥ぐ“クマ剥ぎ”によってスギなどの林業被害も発生します。水産被害としては養魚場に侵入し、ニジマスなどの被害が発生しています。
01-1024x538.png)
02-1-1024x538.png)
03-1024x538.png)
04-1024x538.png)
クマ類の農業被害額の特徴
平成29年度〜令和5年度の被害の特徴
クマ類による農業被害額は、平成29年度から令和5年度までは概ね3億8,000万円から4億6,000万円の範囲で推移していたが、令和5年度には7億4,718万円と前年度比約1.8倍に急増しました(農林水産省)。
-1024x576.jpeg)
主な要因は果樹被害の増加であり、被害額は前年度の7,202万円から令和5年度には2億8,900万円となりました。クマ類(主にツキノワグマ)はクリやカキ、リンゴなどの果実を好むため、特に秋季には大きな果樹被害が発生します。
また、飼料作物への被害(主にヒグマによる)も継続的に発生しており、令和5年度の被害額は2億2,559万円でした。野菜やいも類といった畑作物への被害も近年増加傾向にあり、農地周辺への出没が増加していることが示唆される。
クマ類による農業被害は一部の作物に集中しつつも、被害対象が徐々に広がりつつある。令和5年度のような突出した被害の背景には、餌資源の不作やクマの個体数増加、里山環境の変化などが関係していると考えられ、今後も注意深く動向を見守る必要がある。
被害対策方法
電気柵
ツキノワグマはワイヤーメッシュなどの物理柵を登って越えることができるため、電気柵による被害対策が有効です。電気柵はツキノワグマが柵線に触れることで電流によるショックを与えて、心理的に侵入させないようにする防護柵です。設置場所の地面がコンクリート・アスファルトである場合や乾いている場合では通電性が低くなるため、設置場所の変更や通電性のある素材を敷く必要があります。アースは湿った場所に深く埋め込み、間隔を空けて設置します。電気柵の柵線に雑草が触れると、漏電により効果が弱くなってしまうため、設置後には草刈りなど定期的な点検が必須です。
01.jpeg)
複合柵
複合柵はワイヤーメッシュなどの物理柵と電気柵を組み合わせた防護柵です。複合柵の特徴は物理柵の強度と電気柵の心理的な抑止効果を兼ね備えており、ツキノワグマの侵入をより効果的に防ぐことができます。
引用文献
北海道環境生活部自然環境局野生動物対策課.野生鳥獣による被害調査結果について(令和5年度),https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higai.html(2025-07-01閲覧).
農林水産省.全国の野生鳥獣による農作物被害状況について(令和5年度).https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/index.html(2025-06-20参照).
農林水産省.過年度の農作物被害状況.https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/kanendo_higai.html(2025-06-20参照).